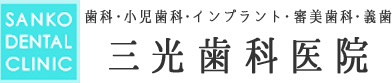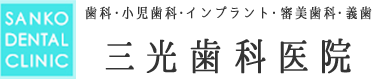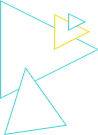 コラム
コラム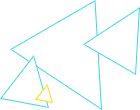
- 2017/03/06
- 院長コラム
脳活動から噛み合わせの違和感を可視化。ODS患者の診断に有効な技術を開発
噛み合わせ自体には医学的な問題がないにもかかわらず、心理的なストレスなどが原因で、噛み合わせに強い違和感を覚える「咬合違和感症候群」(ODS)。ODS患者の口腔の違和感は、原因となるストレスの解消にのみ緩和され、歯科的な治療では症状が改善せず、かえって悪化することが多い、一般的な歯科治療で改善する患者なのか、歯科治療を行ってはいけないODS患者なのか。これは定量的に診断する手法はこれまでになかった。
そんな中、明治大学理工学部電気電子生命学科は、神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔機能修復学講座の研究グループと共同で、脳活動から噛み合わせの違和感を可視化し、ODS患者かどうかを精度よく推定する手法を開発した。研究グループは歯を噛み合わせるという行為に対して強い注意が引き起こされるODS患者の特性に注目。脳の活動を計算する近赤外分析法を用いて、歯を噛み合わせた際の能動的な注意によって引き起こされる脳活動を検出。その結果、ODS患者と非ODS患者での違いが明らかとなった。そこで脳活動波形の変化量からその患者がODSであるかないかを判定させる識別器を作成。92.9%の正確さでODS患者を識別することに成功した。
この技術は、歯科医師にとって定量的なODSの診断基準をもたらすと同時に、不要な歯科治療によるリスクを低減させることができる、また、ODS患者にとっても、脳活動を可視化して捉えることで、違和感の原因が理解しやすくなることは間違いない。適切な治療への移行、QOLの向上につながることが期待される。
あなたへのおすすめ記事

- 2025/11/03
- 院長コラム
- “小児歯科について”
- 詳しく見る

- 2025/10/27
- 院長コラム
- “歯周病と全身のかかわり”
- 詳しく見る

- 2025/10/20
- 院長コラム
- “災害時にこそ大切!お口のケア~備えておくこと 自分でできること~”
- 詳しく見る

- 2025/10/13
- 院長コラム
- 10月17日(金)診療時間変更のお知らせ
- 詳しく見る